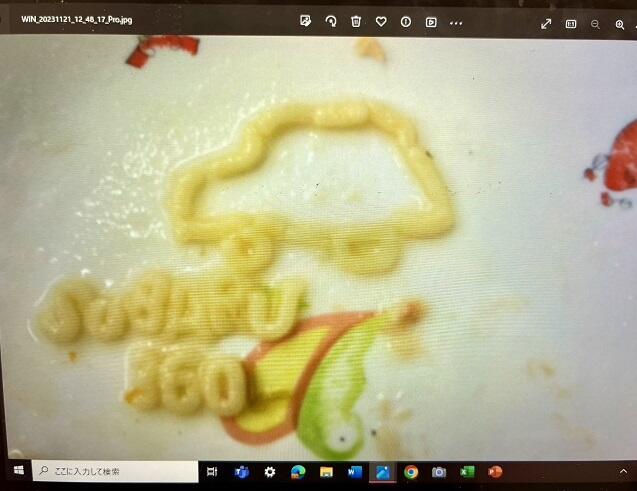文字
背景
行間
校長室から
322 学びは人の数だけ(23.12.5)
ある日、3年生の教室前を通ると、国語で「こそあど言葉」の学習をしています。覗いてみると、活発な発言が聞かれました。阪神タイガースの岡田監督の「アレ(A.R.E)」は、今年の流行語大賞に輝きましたが、コレをネタにしない手はないよなぁ。「こそあど言葉」ばかりで会話する私は、そんなことを思いながら扉を閉めました。算数では2年生の九九の暗唱が佳境を迎えます。パパっと暗算ができる「おみやげ算」という計算方法もあるようです。
実際の生活場面でも、簡単に計算ができると重宝します。例えば、4個入り510円と6個770円のチョコの箱が並んでいたとします。どっちがお得か考える場面は結構あるものです。「510÷4」と「770÷6」は、暗算をすぐにできそうもありませんのでスマホを取り出したくなります。でも、個数の4と6の最小公倍数12で比べると簡単です。1箱510円の方は12個にするためには3箱分で、「510×3=1530」となります。1箱770円の方は「770×2=1540」となりますから、4個セットのほうが若干お得という結果が導き出されます。私の場合、スーパーの酒売り場で、ビールをケースで買ったほうが得か特価表示の6缶パックが得か、おもむろにスマホを取り出してしまいます。みんながわり算で解を求める中に、上の方法など独自の解法にたどり着く子がいたら大いに認め褒めてあげます。
さて、今日は4年生の校外学習。佐原に始まり、野田へ行って醤油づくりを見学します。結構な移動距離ですから出発も早い。でも、どんな驚きや発見をするのか楽しみです。伊能忠敬の制作した地図の精巧さなのか、醤油工場の独特の匂いなのか。感じたことを自分の言葉で考えへと高めてほしいと思います。そういえば、私も小学生の時に行った醤油工場でその匂いに「うっ」となった一人ですが、小さな醤油瓶をもらってうれしかったことばかり思い出してしまいます。
321 和食(23.12.4)
新聞の見開きの全部がかに、カニ、蟹…。生やボイルしたズワイガニやタラバガニの通販広告です。う~ん、魅力的!11月末日締め切りかぁ。悩んだ挙句、私はどうしたでしょうか?年末商戦に突入です。
さて、山口百恵さんが歌った『秋桜』(さだまさし作詞作曲)に「♪こんな小春日和の~穏やかな日は~」という歌詞があります。この「小春日和」は、春のような穏やかで暖かい初冬の陽気を指します。だいたい11月初旬から12月初旬ころの秋から冬へと季節が移ろう時期を言います。
外国でも秋の終わりから初冬にかけての季節の変わり目の暖かな日を表す表現があることを知りました。例えば、英語では「インディアン・サマー」、ドイツ語では「老婦人の夏」、中国語では「秋老虎(秋のトラ)」という言い方をするのだそうです。日本では、もうそろそろ小春日和を使える季節ではなくなり、本格的な冬の始まりとなりますが、移ろいに敏感でありたいと思います。
話は変わりますが、先日講演を聞いて、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されていることを知ったような思い出したような…。今日は登録されて10年目を迎える日だそうです。四季が明確な日本において、豊かな自然を尊び、そこで生まれた習わしが日本伝統の食文化として認められたわけです。その特徴として、「1多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」、一汁三菜を基本とする「2健康的な食生活を支える栄養バランス」、添え物や器などを工夫して「3自然の美しさや季節の移ろいの表現」、そして「4正月などの年中行事との密接なかかわり」を挙げています。毎日の食卓や給食の中にも、こうした思いがたくさん込められているはず。その意識があるかないかで楽しみ方も違ってきそうです。
320 百人に聞きました(23.12.1)
リンゴをかじる画を想像すると、なぜかしら「白雪姫」を思い浮かべてしまいます。ある日、リンゴ農家の人が収穫したリンゴを皮ごと丸かじりする映像がテレビから流れます。隣で見ていた若いリポーターの女性が驚いたような表情をつくります。スタジオのアナウンサーが「歯が丈夫でないとできませんね」と言っています。もしかすると、今はリンゴを丸ごとかぶりつく習慣がなくなっているのかもしれないと思い至りました。皮を剥いて何等分かに切り分けて食べることが多くなりましたから、皮を耳に見立ててウサギのようにした切ったリンゴだって見かけることがなくなりました。一緒にテレビを観ながら隣で、「昔のリンゴは比較的小さかったしね」という言葉もあながち間違っていなさそうです。リンゴを丸かじりした経験のある人を全校450人に聞いたら何割いるのでしょう?
そういえばずっと昔、『クイズ100人に聞きました』なんて番組がありました。司会の関口宏さんが、回答者席のカウンターに体を寄りかからせるポーズを思い出します。ルールは簡単!2つの家族チームから代表者が1人ずつ前に出て早押しで回答するもの。答えが複数あるので、より上位(数が多い回答)の答えを当てると、次の回答権も与えられるというものでした。
例えば、「スイミングスクールに通う小学生100人に聞きました。一番のごちそうと言ったら何?」という問題。この100人が「丸の内のOL」だったり「幼稚園児」だったり「市川のおまわりさん」だったりするわけです。
それでは問題!「すてきな女性(男性)がじっとこちらを見つめていたら?」。お辞儀をする?声をかける?もじもじする?見つめ返す?目をそらす?自分の後ろに誰かがいるのかもしれないと思って振り向く?それとも、逃げる?
12月、日々の逃げ足の速さを加速度的に実感する時季です。
319 鉄道(23.11.30)
休み時間など、自由帳に電車の絵を描いて青やオレンジのラインを塗っている子を時々見かけます。覗き込むと “これは京浜東北線で、こっちが湘南新宿ライン” と教えてくれます。今日の就学時健診に来る子供たちの中にも、電車大好きっ子がきっといるでしょう。こうした鉄道好きを、「乗り鉄」「撮り鉄」などと分類する言葉はよく耳にします。このほかにも、「時刻表鉄」「廃線鉄」「車両鉄」「模型鉄」などたくさんあるそうですが、「駅弁鉄」って何かよい響き。人気アニメ『スラムダンク』のオープニングシーンに登場する江ノ電の踏切は、バックに広がる湘南の海や夕日も含めて聖地となっています。その一方で、ルール無視の人々が迷惑をかける様子も報じられていますが、こうした輩はさすがに撮り鉄の範疇には入らないでしょう。ちなみに、冒頭の児童は「絵描き鉄」?
私が毎日使う東武アーバンパークラインに、11月から新色が登場しました。鮮やかなオレンジ色の帯と濃いベージュのツートーン。でも、車両自体は払い下げ車両のような古さです。8000型で唯一の原型顔として動態保存されていた8111編成が一般営業に就いたらしいのです。どうも珍しい車両のようで、最寄り駅付近の踏切に撮り鉄が集まっていました。ただ素朴な疑問も…。この色の電車がいつここを通過するか、何を調べてわかったのでしょう。
そんな電車に乗りながらよく思うこと。7人掛けのシートが尻型や手すりなどで3対4に分かれていないとき、座った人の感覚次第で微妙なズレが生じます。ある人はある程度余裕のある6人で座ろうと腰を下ろします。でもある人は7人掛けを律義に守ろうとします。すると、6人座った後に園児なら座れそうな狭~い空間が生まれるのです。後から乗ってきた人がこの隙間に座ろうかどうか、一瞬の迷いが感じとれます。時には、そこに申し訳なさそうにお尻を差し込む人がいいます。両側に座る人が少し左右にズレれば済むのですが、一方の人だけが詰めると座り方に不公平感が見えてきてしまうのです。わかりますぅ~?こんなどうでもよいことに心が乱れる…。
318 新聞を開いて(23.11.29)
先日市川市小・中学生新聞感想文コンクールの受賞者が発表された記事を見ました。市川市新聞組合の好意で3年生以上の全学級に2紙が毎日届けられます。全く開かないまま積み上げられているということがないことを祈ります。
その新聞に作家の堂場瞬一さんのインタービューが掲載されていました。小説家になろうと思ったのは、字が読めるようになってすぐのことで、小学校の図書室の本は片っ端から読み、高学年で星新一のSFの世界に夢中になったそうです。意識して小説を書き始めたのは大学生のころだと言いますが、発想の源は新聞にあるようです。“新聞って何でも載っていて興味のないところまでつい読むじゃない。それが意外と記憶に残っている。”と語るように、紙面をめくると様々な情報がどんどん飛び込んできます。好む好まざるにかかわらず目に触れるわけです。これがインターネット情報との大きな違い。難しいことは考えずに、まずは教室に配られた新聞を手元に置いて、眺めてみようとする子供たちが増えてくれるといいなぁと思います。だって、新聞をとっていない家庭がとても多い現代ですから…。家にあるならなおさら!
給食でABCスープが提供された翌日、タブレットを抱えて校長室にやってきた男児の作品が写真のとおり!思わず笑ってしまいます。汁の中から必要なアルファベットマカロニを見つけ出して並べたようです。数字もありますし、車の形はマカロニを千切って並べたようです。もしかすると、「誰か『S』が入っている人いない?」なんて声があったのかも…。どんなに車好きであっても、その行動力と発想、根気に感心です。