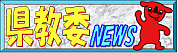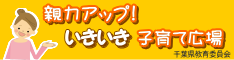【7.12.2新着】
各種たよりに学校だより8号掲載しました。本校が今年度行った「地域の方たちと共に学んだ地域連携行事」
について掲載しました。ご一読お願いします。
【7.12.2新着】
千葉県こどもと親のサポートセンターより
令和7年度サポートルーム(12月~1月)の開催が届きましたので掲載します。
千葉県こどもサポートセンター「12~1月サポルームの開催について」.pdf
【7.11.11新着】
市川市教育委員会学校地域連携推進課より
「第2回サポート講座」開催についての案内を掲載しました。
R7 第2回サポート講座チラシ.pdf
【7.11.6新着】
市川市教育会館からの「バルーンアート教室」参加案内を掲載しました。
バルーンアート.pdf
【7.10.22新着】
R07No4 学校委員会だよりを掲載しました。
学校委員会だより
【7.10.14新着】
PTAより「PTA本部役員募集のご案内」が届きました。
令和8年度 保護者宛 PTA本部役員募集のご案内.pdf
【7.9.29新着】
千葉県子どもと親のサポートセンターよりお知らせが2つ届きました。ご一読ください。
7.9.19千葉県子サポ、サポート広場のお知らせ.pdf
7.9.19千葉県子サポ進路選択サポートセミナー.pdf
【7.9.19新着】
学校だより6号部活動地域展開について掲載しました。
各種たよりの中にあります。ご一読ください。
【7.9.19新着】
市川市では例年「公開研究発表会」を開催しており、本年度も実施いたします。
詳細につきましては下記文書をご確認ください。参加を希望される場合は、添付の申込書を印刷し、ご記入のうえ学級担任までご提出ください。印刷が難しい場合は、10月2日までに教頭へお電話ください。
2025年度 千教研市川支会公開研究発表会について.pdf
2025年度 公開研・定例研一覧表.pdf
【7.9.18新着】
子ども家庭相談課からのお知らせです。
「ゲームネット依存 熱中するこどもの気持ちと保護者の対応について」
ご参加いただける方は、下記チラシよりお申し込みください。
講演会のお知らせ.pdf
【7.9.16新着】
生徒指導だより2号を配付しました。こちらにも掲載させていただきます。
今後の体操服登下校について書いてありますので、御一読ください 。
R7生徒指導だより②.pdf
【7.9.12新着】
PTA 意識調査アンケートの結果について
PTA意識調査アンケート集計結果.pdf
【7.9.3新着】
市川市教育委員会から科学作品展のお知らせが
来ています。ご一読ください。
R7科学展の案内.pdf
【7.9.2新着】
市川市教育委員会から不登校親の会から「ichiここ」のお知らせが
来ています。ご一読ください。
ichiここお知らせ.pdf
【7.9.1新着】
千葉県子どもと親のサポートセンターから不登校の生徒の進路のことでお困りの方へ
お知らせが来ています。ご一読ください。
千葉県子サポ【不登校児童生徒進路サポートセミナーのお知らせ】.pdf
【7.8.5新着】
千葉県子どもと親のサポートセンターから不登校や学校のことでお困りの方へ
お知らせが来ています。ご一読ください。
千葉県子どもと親のサポートセンターよりお知らせ7.7.25.pdf
【7.7.22新着】
終業式校長講話
グローカル、ボランティア、非認知能力の話をしました。ぜひご覧ください。
7.7.18終業式講話.pdf
【7.7.18新着】
千葉県教育委員会の窓口です。心配なことがある場合は利用してください。
教職員の児童生徒に対するわいせつセクハラ相談窓口
【7.7.11新着】
「SNS青少年非行防止のチラシ」
千葉県環境生活部県民生活課より来ています。夏休み前にご家庭でお子様とご一読ください。
R7青少年非行防止チラシ.pdf
【7.7.10新着】
「千葉県版不登校児童生徒保護者のためのサポートガイド」
千葉県教育委員会のチラシです。ご覧ください。
千葉県版不登校児童生徒保護者のためのサポートガイド.pdf
【7.7.7新着】
「親子の絆を育むメディアリテラシー」
市川市教育委員会 学校地域連携推進課よりお知らせです。令和7年度 家庭教育講演会を別添のチラシのとおり開催いたします。お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。たくさんのご応募お待ちしています。
市川市教育委員会 学校地域連携推進課
R7 家庭教育講演会.pdf
【7.6.30】お茶会のご案内
~子育て奮闘中の皆さんに~興味ある方はPDFをご覧ください。
7.19お茶会.pdf
【7.6.16新着】子育てに関する地域からのお誘いを掲載しました。興味ある方はPDFをご覧ください。
「不登校」「学校ぎらい」で悩んでいる人のお茶会へのお誘い
6.24お茶会.pdf
「ベルフラワー」第4回子育て講演会へのお誘い
9.6フラワーベル第4回子育て講演会.pdf
青少年自らが個人情報を適切に取り扱うための対策について
02.リーフレット-.pdf
第一中学校「生活の心得」
(R6改訂).pdf
非常変災時における学校対応(市川市共通).pdf
悩みや困ったことがある人はこちらへ
小中学生の相談窓口.pdf
市川市学校部活動のガイドライン
R6 部活動活動方針.pdf

↓ ドリルパーク入口

ドリルパークへの入り方.pdf15